C:東京都指定名勝・薬師池/七国山の里山めぐり
2020.02.09
C:東京都指定名勝・薬師池/七国山の里山めぐり
(薬師池コース)
七国山は128メートルと低い山だが、町田市のほぼ中央に位置し、多摩丘陵南部の丘陵地帯を形成している。高度成長期の著しい都市化の波に対し、ここ七国山地区は、東京都第一号の風致地区(1961年)、緑地保全地区(1965年)に指定され、雑木林、畑、谷戸の田んぼが残されて、里山の雰囲気そのままの町田の財産である。
冬のこの時期は雑木林のコナラやクヌギが葉を落とし、緩やかな丘陵地形が現れ、畑と農道の小径からは秩父や丹沢の山並みと富士、七国山からはスカイツリーまでも見渡せる。
薬師池公園の北駐車場からスタート(10:00)。地元の鎮守・野津田神社を参拝し、神社脇の長閑な畑地を右手に野津田公園の緑と華厳院を見ながら気持ちよく歩く。天気も良く、丹沢の山並みと富士山がくっきりと現れた。町田ぼたん園前からは秩父の山並みが見え、道の横の畑の窪地は平安時代の古代東海道ルートと言われている。
七国山ファーマーズセンターで小休止後、「ファーム七国山」の横のちょっとワイルドな小径を進み、鐘楼を経て野津田薬師堂へ向かう。
野津田薬師堂は約1,300年前の行基・開基とされ、町田市最古の平安時代の木造佛(市文化財)を有
する。参道の大銀杏も見ごたえがある。参道の階
段を降り薬師池公園へ出る。
薬師池公園は北条氏照により作られた溜め池(1590年)を中心に、鎌倉街道沿いの細長い暖沢谷戸を利用した谷戸田であった。田んぼは菖蒲田と大賀ハス田へ、畑地は梅林へ。周辺の雑木林とともに武蔵野の面影をよく残した里山公園(1976年)として生まれ変わった。「新東京百景」、「東京都指定名勝」、「日本の歴史公園100選」の3つの指定を受け、町田市を代表する公園である。
昼食を農家料理「高宮」で食べ、午後をスタート。4月にオープン予定のウェルカムゲートの工事風景を見て七国山(128m)へ向かう。
町田市の史跡となっている鎌倉井戸では、「新田義貞が馬に水を飲ませるために掘らせた」との伝説に対して参加者のみなさまから活発なご意見があった。鎌倉井戸からは鎌倉街道上ノ道を下る。深い掘割状の古道として、山林は緑地保全地域で「NPO七国山を考える会」のみなさまが管理されている。その広場小径を歩き、カフェ・ガーデン「風見鶏」の道に出た。
さらに、町田ぼたん園に向かい、ここで小休止と庭園内を散策。ここは、明治時代の自由民権運動の指導者であった石阪昌孝の屋敷跡であるとの説明板を見る。ぼたん園からの道を下り、薬師が丘団地へ戻るとほっとするくらい暖かくなる.。暖沢谷戸の名前の通りである。薬師池公園北駐車場へ戻り解散した(15:00)。

富士の見える畑と農道

秩父の山並みと平安の東海道

野津田薬師堂への小径

町暖沢谷戸の里山・薬師池公園

薬師池公園

田最古の野津田薬師堂を説明

鎌倉井戸

鎌倉井戸から鎌倉街道上ノ道へ

鎌倉街道、掘割状の道跡
(薬師池コース)
講師:NPOみどりのゆび田邊博仁
七国山は128メートルと低い山だが、町田市のほぼ中央に位置し、多摩丘陵南部の丘陵地帯を形成している。高度成長期の著しい都市化の波に対し、ここ七国山地区は、東京都第一号の風致地区(1961年)、緑地保全地区(1965年)に指定され、雑木林、畑、谷戸の田んぼが残されて、里山の雰囲気そのままの町田の財産である。
冬のこの時期は雑木林のコナラやクヌギが葉を落とし、緩やかな丘陵地形が現れ、畑と農道の小径からは秩父や丹沢の山並みと富士、七国山からはスカイツリーまでも見渡せる。
薬師池公園の北駐車場からスタート(10:00)。地元の鎮守・野津田神社を参拝し、神社脇の長閑な畑地を右手に野津田公園の緑と華厳院を見ながら気持ちよく歩く。天気も良く、丹沢の山並みと富士山がくっきりと現れた。町田ぼたん園前からは秩父の山並みが見え、道の横の畑の窪地は平安時代の古代東海道ルートと言われている。
七国山ファーマーズセンターで小休止後、「ファーム七国山」の横のちょっとワイルドな小径を進み、鐘楼を経て野津田薬師堂へ向かう。
野津田薬師堂は約1,300年前の行基・開基とされ、町田市最古の平安時代の木造佛(市文化財)を有
する。参道の大銀杏も見ごたえがある。参道の階
段を降り薬師池公園へ出る。
薬師池公園は北条氏照により作られた溜め池(1590年)を中心に、鎌倉街道沿いの細長い暖沢谷戸を利用した谷戸田であった。田んぼは菖蒲田と大賀ハス田へ、畑地は梅林へ。周辺の雑木林とともに武蔵野の面影をよく残した里山公園(1976年)として生まれ変わった。「新東京百景」、「東京都指定名勝」、「日本の歴史公園100選」の3つの指定を受け、町田市を代表する公園である。
昼食を農家料理「高宮」で食べ、午後をスタート。4月にオープン予定のウェルカムゲートの工事風景を見て七国山(128m)へ向かう。
町田市の史跡となっている鎌倉井戸では、「新田義貞が馬に水を飲ませるために掘らせた」との伝説に対して参加者のみなさまから活発なご意見があった。鎌倉井戸からは鎌倉街道上ノ道を下る。深い掘割状の古道として、山林は緑地保全地域で「NPO七国山を考える会」のみなさまが管理されている。その広場小径を歩き、カフェ・ガーデン「風見鶏」の道に出た。
さらに、町田ぼたん園に向かい、ここで小休止と庭園内を散策。ここは、明治時代の自由民権運動の指導者であった石阪昌孝の屋敷跡であるとの説明板を見る。ぼたん園からの道を下り、薬師が丘団地へ戻るとほっとするくらい暖かくなる.。暖沢谷戸の名前の通りである。薬師池公園北駐車場へ戻り解散した(15:00)。
(田邊博仁写真:井上メイ子)

富士の見える畑と農道

秩父の山並みと平安の東海道

野津田薬師堂への小径

町暖沢谷戸の里山・薬師池公園

薬師池公園

田最古の野津田薬師堂を説明

鎌倉井戸

鎌倉井戸から鎌倉街道上ノ道へ

鎌倉街道、掘割状の道跡
B:鶴川の名家・今も残る里山の中の古民家回廊
2020.02.09
B:鶴川の名家・今も残る里山の中の古民家回廊
(鶴川コース)
講師:鶴川インバウンドを考える会
陶山愼治
Bグループは町田から小田急線で2つ目の鶴川駅集合。地元育ちで老人介護施設等の経営をしている陶山さんの案内。
駅から芝溝街道(津久井道)に出て、途中からその旧道に入る。「妙行寺」が左手に見える。新道を造るため参道が短くなり、入口が超急な階段になってしまっている。
鈴木工務店。代々受け継いでいる築150年の茅葺古民家がある。「可喜庵」という。茶室風な趣のある小ぶりな家だ。時々催し場に使用しているとか。
新道に戻って妙行寺脇の坂道を上る。庭の紅白の梅が春を告げている。本堂の蓮の壁画が可愛らしい。南側の真光寺川の谷の向うに三輪の小山の眺望が美しい。裏山を登り切ると西に富士山のてっぺんが白く見える。緑泥片岩の中世の石塔片や五輪塔が集められている場所がある。鎌倉早ノ道に近く義経に関する伝説も数多く残っている。さらに山道に入る。下からは電車の音が聞こえるのだが、この散歩道はとても心地良い。「能ヶ谷空と緑の森公園」さくら広場に出る。去年東京を直撃した台風で、大人3人抱えもある桜が倒れ、切株が痛々しい。
介護施設の悠々園から新興住宅地や家庭菜園の間の道を通って「能ヶ谷神社」へ。
鶴川第2小の前を通って築153年の「みんなの古民家」前に出る。最近、茅葺の屋根を葺き替えて、小屋根と屋根中央の金属板の意匠がモダンな印象を与えている。当主・石川さんと息子さんが民泊事業を始めて“刀剣女子”の聖地になっているという。
白洲次郎・正子の旧邸宅である茅葺の「武相荘」。引っ越し時の昭和17年、近くには7軒の農家しかなかったという。和風の農家を洋風に、とっても優雅に素敵に暮らしていた様子がうかがわれる。ここで、武相荘監修のお弁当の昼食。
「香山園(かごやまえん)」に出る。旧神蔵家の邸宅。明治期より神蔵中風灸治所として、月1回全国から患者が集まったという。現在の建物は「瑞香閣」といい、明治39年鈴木工務店が建てた。平屋純和風の書院造り。136坪。広い池泉回遊式庭園があり、奥に横穴古墳群や小円墳もある。私設美術館だったが最近市に移管されたらしい。駅に戻って終了。
近頃「サステナビリティ」という言葉を目にする。「持続可能性」と訳されるが、地球規模の資源の枯渇が問題視され、その反省から使い捨てのライルスタイルからの変換の概念である。今日の4軒の古民家はまさにこの精神の具現である。町田の地に皆が利用できる形で残されたのは誇らしい。うららかな良い一日だった。
(N K写真:小川峰文ほか)

可喜庵

妙行寺本堂

能ヶ谷神社社殿

武相荘

香山園瑞香殿

香山園池泉回遊式庭園
A:町田商店街・老舗と歴史の道
2020.02.09
A:町田商店街・老舗と歴史の道
(鎌倉街道&絹の道)
(町田駅周辺の商店街コース)
町田ってどんなところ?市の顔である町田駅周辺には、近代的な大型店舗が立ち並び、大変な賑わいを見せています。その中には何十年も前から続いている個性的な老舗も見られ、商業都市としての新旧を感じる商店街は、遠く戦国時代に開かれた原町田宿に始まっています。また、郊外には多摩丘陵の四季折々の豊かな自然、昔ながらの里山風景と古道などがあり、自然遺産・文化遺産を巡る楽しみもあります。
この新旧、都会と田舎の魅力がバランスよく融合した町田市の魅力を探ろうと、「町田駅周辺の商店街コース」は歴史古道研究家の宮田太郎さんのご案内です。「鎌倉古街道」や幕末の「絹の道」と、その発展がもたらした駅周辺の商店街や賑わいを探訪しました。
スタートは小田急町田駅東口の「カリヨン広場」から。ここには町田の商業の発展に貢献した「絹の道」の碑があります。1859年に横浜港が開港すると、多摩地域の生糸の集積地であった八王子から横浜への運搬ルートが「絹の道」“幕末のシルクロード”と呼ばれ、町田はその重要な中継地となりました。
ここから小田急線第一踏切を越えると鎌倉街道“秩父山の道”を北西方向へ進み、専門学校なども立つ住宅街、「馬頭観音」を経て「町田シバヒロ(芝生広場)」で休憩。“馬”といえば、その昔生糸を運んだ「絹の道」は荷馬車が主役で、創業130年余を誇る馬肉専門店「柿島屋」は歴史の名残でもあります。ここから府中方面を背にして鎌倉街道“上の道”に入り、小田急線第二踏切を越えると中世・原町田宿成立の起点(二つの鎌倉街道のY字合流点)に。今では「サルビア」の愛称で親しまれる民間交番が立ち、裏手には小さな池「まちだの泉」があります。
原町田大通りを渡ると、町田有数の賑わいを見せる原町田中央通りには「河原本店」(明治28年創業)、「柾屋商店」、時代に合わせた製菓材料でも知られる「富澤商店」など老舗乾物店が軒を並べます。河原本店では店主ご夫妻に昆布の種類や産地の興味深い話を聞きながら、料理好きは品選びに夢中でした。
それにしても、なぜこの街道には乾物店が多いのか?絹の道を通って横浜で生糸を荷下ろしした帰りに、保存しやすい海産物や肥料、舶来品などを仕入れて戻り、商うようになったのです。また、物資だけでなく外国の思想や文化をも伝える中継点となりました。横浜開港によって来日した英国人写真家F.ベアトが撮影した幕末の原町田中央通り4丁目付近の写真も残っています。
さらに進むと、商店街に分け入るように境内を構える「浄運寺」には、「原町田七福神」のひとつ「毘沙門天」がぽつねんと立ち、目をひきます。

往時の資料と比較して地形を説明する宮田講師

二つの鎌倉街道のY字合流点には民間交番が

道路が合流した三角の地形に合わせて舟型のパブが!

乾物の老舗「河原本店」のご当主から興味深い説明をいただく
市内に点在するあとの「福禄寿」や「布袋尊」などを巡って、約2kmの開運祈願も街歩きの楽しみを膨らませます。
しばらくして、先を行く講師の宮田さんの声に注目すると、「富澤商店」近くの道路に珍しい“街道の鍵の手”を発見。宿場町などに残された往時のままの曲がり角で、街道ウォーカーの“萌えポイント”になっている珍しい地形なのだとか。
商店街には和菓子の「中野屋」、自家製焼豚が人気の「守屋精肉店」など老舗店に加えて、数多くの古着屋が集まり、“古着の聖地”と言われる町田の顔があることも知られています。古さを新鮮な楽しみに変える感覚が根付いているのです。
さてここあたりでランチを、ということで、総勢50名余りのメンバーは、いくつかのグループに分かれてランチハンティングです。各地の名産品ショップのある「ぽっぽ町田」前の広場では、早くもカフェに陣取るグループもいて、私たちはすぐ先の「仲見世商店街」へ。
関東大震災後の古物市場から、戦後に「国際
マーケット」として発展した商店街で、長さ約100m、道幅2mほどのアーケード街の両側には新旧様々な飲食店や商店が立ち並び、さながら東南アジアの市場の雰囲気です。その中程にあるタイ料理の「旅人食堂町田屋台店」がお目当て。この商店街の雑多でパワフルな楽しさを体現しているような現地感覚で、カオマンガイや生春巻き、もちろんトムヤムクンも本場の味と評判です。
午後からは、これまで午前中に歩いた鎌倉街道上ノ道(シバヒロ付近から小田急線第二踏切を経て、老舗が軒を並べる原町田中央通りを下る)が、さらに延びる往時の推定ルートを探索することになります。
その前に、ちょっと欲張って「国際版画美術館」方面へ抜ける公民館通りを歩いて、レンガの外装が美しい「町田市民文学館」を見学。今では希少な活版印刷を手掛ける「新星舎印刷所」に立ち寄り、ここならではの貴重なお話を伺うにつけ、町田にしっかり根付いている文化の気風を感じたことでした。

赤い椿が満開の「浄運寺」

「旅人食堂町田屋台店」は現地感覚満点

仲見世商店街は”西のアメ横”ともいわれる

「まちの駅ぽっぽ町田」では蚤の市が開かれていた

看板も楽しい「守屋精肉店」

「町田市民文学館」では三島由紀夫展が開催中

「新星舎印刷所」を仕切る名取社長に話を伺う
仲見世商店街は”西のアメ横”ともいわれる原町田中央通りが町田街道と出合う地点近くにJR横浜線の高架橋があります。ここ辺りが問題の「鎌倉街道上ノ道」の推定ルートにつながるのでしょうか。
周囲を見回すと、目前に「町田天満宮」が。まずは学問の神様・菅原道真公を祀る神社にお参りしてから。おりからの白い梅の花が香って、境内で毎月1日に開かれる「がらくた骨董市」の賑わいが蘇ります。 ここでも七福神の「恵比寿神」が一行を迎えてくれました。
先ほどの高架橋にもどって眺める町田の中心街。
そこに見えたのは、ホテルや高層商業ビルが立ち並び、歩いて来た活気あふれる新旧の商店がその足元を縫う都会の顔でした。往時の鎌倉街道上の道が町田を経て向かう八王子方面はどんな時代の変化を見せたのでしょうか。
そろそろお茶の時間です。仲見世商店街近くの老舗「ひじかた園」二階の茶房では、店主ご夫妻に珍しいマテ茶のおもてなしをいただき、人出がいっそう増えた午後の商店街を後にしました。

「町田天満宮」には立派な牛の像が守り神のごとくに

太宰府と同様に白梅が香る

JR 横浜線の高架橋上から古道の推定ルートに思いを馳せる

「ひじかた園」の茶房でお茶のおもてなし。後方は当主ご夫妻

「鎌倉街道上の道」の推定ルートに想いを

「シバヒロ」で全員集合写真高架橋から
(鎌倉街道&絹の道)
(町田駅周辺の商店街コース)
講師:歴史古道研究家宮田太郎
みどりのゆび神谷由紀子
町田ってどんなところ?市の顔である町田駅周辺には、近代的な大型店舗が立ち並び、大変な賑わいを見せています。その中には何十年も前から続いている個性的な老舗も見られ、商業都市としての新旧を感じる商店街は、遠く戦国時代に開かれた原町田宿に始まっています。また、郊外には多摩丘陵の四季折々の豊かな自然、昔ながらの里山風景と古道などがあり、自然遺産・文化遺産を巡る楽しみもあります。
この新旧、都会と田舎の魅力がバランスよく融合した町田市の魅力を探ろうと、「町田駅周辺の商店街コース」は歴史古道研究家の宮田太郎さんのご案内です。「鎌倉古街道」や幕末の「絹の道」と、その発展がもたらした駅周辺の商店街や賑わいを探訪しました。
スタートは小田急町田駅東口の「カリヨン広場」から。ここには町田の商業の発展に貢献した「絹の道」の碑があります。1859年に横浜港が開港すると、多摩地域の生糸の集積地であった八王子から横浜への運搬ルートが「絹の道」“幕末のシルクロード”と呼ばれ、町田はその重要な中継地となりました。
ここから小田急線第一踏切を越えると鎌倉街道“秩父山の道”を北西方向へ進み、専門学校なども立つ住宅街、「馬頭観音」を経て「町田シバヒロ(芝生広場)」で休憩。“馬”といえば、その昔生糸を運んだ「絹の道」は荷馬車が主役で、創業130年余を誇る馬肉専門店「柿島屋」は歴史の名残でもあります。ここから府中方面を背にして鎌倉街道“上の道”に入り、小田急線第二踏切を越えると中世・原町田宿成立の起点(二つの鎌倉街道のY字合流点)に。今では「サルビア」の愛称で親しまれる民間交番が立ち、裏手には小さな池「まちだの泉」があります。
原町田大通りを渡ると、町田有数の賑わいを見せる原町田中央通りには「河原本店」(明治28年創業)、「柾屋商店」、時代に合わせた製菓材料でも知られる「富澤商店」など老舗乾物店が軒を並べます。河原本店では店主ご夫妻に昆布の種類や産地の興味深い話を聞きながら、料理好きは品選びに夢中でした。
それにしても、なぜこの街道には乾物店が多いのか?絹の道を通って横浜で生糸を荷下ろしした帰りに、保存しやすい海産物や肥料、舶来品などを仕入れて戻り、商うようになったのです。また、物資だけでなく外国の思想や文化をも伝える中継点となりました。横浜開港によって来日した英国人写真家F.ベアトが撮影した幕末の原町田中央通り4丁目付近の写真も残っています。
さらに進むと、商店街に分け入るように境内を構える「浄運寺」には、「原町田七福神」のひとつ「毘沙門天」がぽつねんと立ち、目をひきます。

往時の資料と比較して地形を説明する宮田講師

二つの鎌倉街道のY字合流点には民間交番が

道路が合流した三角の地形に合わせて舟型のパブが!

乾物の老舗「河原本店」のご当主から興味深い説明をいただく
市内に点在するあとの「福禄寿」や「布袋尊」などを巡って、約2kmの開運祈願も街歩きの楽しみを膨らませます。
しばらくして、先を行く講師の宮田さんの声に注目すると、「富澤商店」近くの道路に珍しい“街道の鍵の手”を発見。宿場町などに残された往時のままの曲がり角で、街道ウォーカーの“萌えポイント”になっている珍しい地形なのだとか。
商店街には和菓子の「中野屋」、自家製焼豚が人気の「守屋精肉店」など老舗店に加えて、数多くの古着屋が集まり、“古着の聖地”と言われる町田の顔があることも知られています。古さを新鮮な楽しみに変える感覚が根付いているのです。
さてここあたりでランチを、ということで、総勢50名余りのメンバーは、いくつかのグループに分かれてランチハンティングです。各地の名産品ショップのある「ぽっぽ町田」前の広場では、早くもカフェに陣取るグループもいて、私たちはすぐ先の「仲見世商店街」へ。
関東大震災後の古物市場から、戦後に「国際
マーケット」として発展した商店街で、長さ約100m、道幅2mほどのアーケード街の両側には新旧様々な飲食店や商店が立ち並び、さながら東南アジアの市場の雰囲気です。その中程にあるタイ料理の「旅人食堂町田屋台店」がお目当て。この商店街の雑多でパワフルな楽しさを体現しているような現地感覚で、カオマンガイや生春巻き、もちろんトムヤムクンも本場の味と評判です。
午後からは、これまで午前中に歩いた鎌倉街道上ノ道(シバヒロ付近から小田急線第二踏切を経て、老舗が軒を並べる原町田中央通りを下る)が、さらに延びる往時の推定ルートを探索することになります。
その前に、ちょっと欲張って「国際版画美術館」方面へ抜ける公民館通りを歩いて、レンガの外装が美しい「町田市民文学館」を見学。今では希少な活版印刷を手掛ける「新星舎印刷所」に立ち寄り、ここならではの貴重なお話を伺うにつけ、町田にしっかり根付いている文化の気風を感じたことでした。

赤い椿が満開の「浄運寺」

「旅人食堂町田屋台店」は現地感覚満点

仲見世商店街は”西のアメ横”ともいわれる

「まちの駅ぽっぽ町田」では蚤の市が開かれていた

看板も楽しい「守屋精肉店」

「町田市民文学館」では三島由紀夫展が開催中

「新星舎印刷所」を仕切る名取社長に話を伺う
仲見世商店街は”西のアメ横”ともいわれる原町田中央通りが町田街道と出合う地点近くにJR横浜線の高架橋があります。ここ辺りが問題の「鎌倉街道上ノ道」の推定ルートにつながるのでしょうか。
周囲を見回すと、目前に「町田天満宮」が。まずは学問の神様・菅原道真公を祀る神社にお参りしてから。おりからの白い梅の花が香って、境内で毎月1日に開かれる「がらくた骨董市」の賑わいが蘇ります。 ここでも七福神の「恵比寿神」が一行を迎えてくれました。
先ほどの高架橋にもどって眺める町田の中心街。
そこに見えたのは、ホテルや高層商業ビルが立ち並び、歩いて来た活気あふれる新旧の商店がその足元を縫う都会の顔でした。往時の鎌倉街道上の道が町田を経て向かう八王子方面はどんな時代の変化を見せたのでしょうか。
そろそろお茶の時間です。仲見世商店街近くの老舗「ひじかた園」二階の茶房では、店主ご夫妻に珍しいマテ茶のおもてなしをいただき、人出がいっそう増えた午後の商店街を後にしました。
(横山禎子写真:松美里瑛子)

「町田天満宮」には立派な牛の像が守り神のごとくに

太宰府と同様に白梅が香る

JR 横浜線の高架橋上から古道の推定ルートに思いを馳せる

「ひじかた園」の茶房でお茶のおもてなし。後方は当主ご夫妻

「鎌倉街道上の道」の推定ルートに想いを

「シバヒロ」で全員集合写真高架橋から
「皆の好きな都会・里山ミックスのまち:町田」
2020.02.09
まちだフットパスウォーク「皆の好きな都会・里山ミックスのまち:町田」
町田での10周年ということで、9日のフットパスウォークも、新しい問題提起を行うことにしました。小野路など町田の里山フットパスは有名になりましたが、今回は里山と町田の中心街を繋ぐコースを提案してみることにしました。

町田の魅力は、里山と都会が同居していることだと言われています。この「里山と都会を併せ持つ」ということは町田ばかりでなく、全国を回ってみて若い人や移住者に人気の地域はこの条件下にあることが多いことがわかりました。特にコロナ以後、この条件は人気になっています。
しかし今、その町田の「里山都会同居」のディープな魅力を形成している街中の老舗商店街が消えようとしています。これを失ったら今の味わい深い町田はなくなってしまいます。一方、町田愛にあふれたキープウィルのような若い起業家グループや鶴川インバウンドの会のような地域のグループも育っており、今町田全体で里山と街中を繋ごうというコンセンサスができつつあります。
このコンセプトに従って今回は5つのコースを選びました。また「ナイトフットパス」でも日本フットパス協会専任理事の尾留川さんが選抜した街中の特選コースを楽しんでいただきました。5コースの詳細はそれぞれの担当者の方たちに報告をしていただきますが、やはり初めての試みだったので、里山フットパスをイメージしてきた方にはまだ想いが十分届かなかった部分もあったかもしれませんが。ただ町田のフットパスの新しい展開を示す第一歩とはなりました。

都会里山ミックスのまちだ

古いものを残そう

老舗は町田のディープな魅力
このコース設定を通して、お茶のひじかた園、活版印刷の新星舎印刷所、乾物の河原本店などの貴重な老舗、そして武相庵やstriなどの町田に未来をもたらす若いビジネスグループと知り合うことができました。
みどりのゆびも古い町田、自然のままの町田の保全を基調としながら、新しい可能性を目指して挑戦していきたいと思います。
町田での10周年ということで、9日のフットパスウォークも、新しい問題提起を行うことにしました。小野路など町田の里山フットパスは有名になりましたが、今回は里山と町田の中心街を繋ぐコースを提案してみることにしました。

町田の魅力は、里山と都会が同居していることだと言われています。この「里山と都会を併せ持つ」ということは町田ばかりでなく、全国を回ってみて若い人や移住者に人気の地域はこの条件下にあることが多いことがわかりました。特にコロナ以後、この条件は人気になっています。
しかし今、その町田の「里山都会同居」のディープな魅力を形成している街中の老舗商店街が消えようとしています。これを失ったら今の味わい深い町田はなくなってしまいます。一方、町田愛にあふれたキープウィルのような若い起業家グループや鶴川インバウンドの会のような地域のグループも育っており、今町田全体で里山と街中を繋ごうというコンセンサスができつつあります。
このコンセプトに従って今回は5つのコースを選びました。また「ナイトフットパス」でも日本フットパス協会専任理事の尾留川さんが選抜した街中の特選コースを楽しんでいただきました。5コースの詳細はそれぞれの担当者の方たちに報告をしていただきますが、やはり初めての試みだったので、里山フットパスをイメージしてきた方にはまだ想いが十分届かなかった部分もあったかもしれませんが。ただ町田のフットパスの新しい展開を示す第一歩とはなりました。

都会里山ミックスのまちだ

古いものを残そう

老舗は町田のディープな魅力
このコース設定を通して、お茶のひじかた園、活版印刷の新星舎印刷所、乾物の河原本店などの貴重な老舗、そして武相庵やstriなどの町田に未来をもたらす若いビジネスグループと知り合うことができました。
みどりのゆびも古い町田、自然のままの町田の保全を基調としながら、新しい可能性を目指して挑戦していきたいと思います。
(神谷由紀子写真:松美里瑛子)
町田まちなかツアー
2019.12.08
町田まちなかツアー
12 月8 日(日)天気:晴 参加者:10 名
講師:宮田 太郎(古街道研究家)
昨日とは打って変わって穏やかな小春日和。来年2月に行われる日本フットパス協会10周年記念、東京町田大会の1コース「町田の商店街の老舗店と歴史ある古街道を歩く」の下見を兼ねての散策です。
まず小田急線町田駅前カリヨン広場からの出発。第一踏切の左を斜めに入る道は鎌倉古道山ノ道。この先は秩父から群馬に繋がっているらしい。「ブラたもり」ではないが、土地の高低差をチェックしながらタチ山の場所を確認。普段利用しているのに気がつかなかったが、町田駅から玉川学園方面は急な下り坂になっているのが良くわかる。シバヒロ広場から今度は奥州にも繋がっていたという鎌倉街道早ノ道を辿って二叉路に出る。ここは山ノ道と早ノ道の分岐点となっている。ここからが昔からの商店街。絹の道と言われる、八王子から横浜に繋がる道の中間に位置している。ベアトや明治・大正・昭和の写真と今の道を見比べながら変遷を確認する。浄運寺・ぽっぽ町田の骨董市・勝楽寺・町田天満宮に立ち寄って今日の散策は終了。
最後に忘年会を兼ねて新しくできた「STRI」というレストランで遅めのビュッフェランチ。いまどきのおしゃれなお店でなかなか予約出来ないらしい。このビルは最近出来たもので、4 階に若い起業家のためのコワ―キング&シェアオフィス、6 階にインターネットカフェが入っていて、もしかしたら六本木ヒルズの町田仕様ミニ版?と、連想してしまった。
町田は駅前の都会と、そこから車で15分の場所にある「みどりのゆび」の拠点でもある隠れ里の様な里山が隣り合っている。今日の散策でも、古くから続いてがんばっている乾物屋さん、お肉屋さん、古着屋さん、仲見世通りのお店屋さんと、このレストランビルのように新しい若者向けのお店が隣り合っている。しかもそれが面白いカオスを醸し出している。あらためて、町田は異質なものを融合させるエネルギーを内包し、新しい魅力を生み出していく町だと実感した
この次は夜の散策をしたいという要望もあって期待したい。
(N.K)

12 月8 日(日)天気:晴 参加者:10 名
講師:宮田 太郎(古街道研究家)
昨日とは打って変わって穏やかな小春日和。来年2月に行われる日本フットパス協会10周年記念、東京町田大会の1コース「町田の商店街の老舗店と歴史ある古街道を歩く」の下見を兼ねての散策です。
まず小田急線町田駅前カリヨン広場からの出発。第一踏切の左を斜めに入る道は鎌倉古道山ノ道。この先は秩父から群馬に繋がっているらしい。「ブラたもり」ではないが、土地の高低差をチェックしながらタチ山の場所を確認。普段利用しているのに気がつかなかったが、町田駅から玉川学園方面は急な下り坂になっているのが良くわかる。シバヒロ広場から今度は奥州にも繋がっていたという鎌倉街道早ノ道を辿って二叉路に出る。ここは山ノ道と早ノ道の分岐点となっている。ここからが昔からの商店街。絹の道と言われる、八王子から横浜に繋がる道の中間に位置している。ベアトや明治・大正・昭和の写真と今の道を見比べながら変遷を確認する。浄運寺・ぽっぽ町田の骨董市・勝楽寺・町田天満宮に立ち寄って今日の散策は終了。
最後に忘年会を兼ねて新しくできた「STRI」というレストランで遅めのビュッフェランチ。いまどきのおしゃれなお店でなかなか予約出来ないらしい。このビルは最近出来たもので、4 階に若い起業家のためのコワ―キング&シェアオフィス、6 階にインターネットカフェが入っていて、もしかしたら六本木ヒルズの町田仕様ミニ版?と、連想してしまった。
町田は駅前の都会と、そこから車で15分の場所にある「みどりのゆび」の拠点でもある隠れ里の様な里山が隣り合っている。今日の散策でも、古くから続いてがんばっている乾物屋さん、お肉屋さん、古着屋さん、仲見世通りのお店屋さんと、このレストランビルのように新しい若者向けのお店が隣り合っている。しかもそれが面白いカオスを醸し出している。あらためて、町田は異質なものを融合させるエネルギーを内包し、新しい魅力を生み出していく町だと実感した
この次は夜の散策をしたいという要望もあって期待したい。
(N.K)

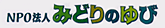
 2020.02.09 09:03
|
2020.02.09 09:03
| 


