【緑地管理報告 6/1(日)】
2025.06.02
6月1日(日) 9:30―11:30 天気:晴れ
参加者:6人
昨日は雨が降っていましたが今日は晴れ間が見える天気で一安心でした。
6月から開始が30分早い夏時間の集合となりました。
最初に管理地全体をみんなで歩いてまわり、緑地の状況を確認いたしました。
そして、今後の草刈り等管理の計画をみんなで考えました。
整備の中心は草刈りでした。ブタクサは根っこから丁寧に刈り取りました。
これにより、根から再び出てくることがないようになります。
刈り取った草は積み重ねておきました。
また刈払機を使い布田道から見える草地を重点的に刈ることにしました。
ここを歩く人が気持ちよく見えることを意図しています。
また奥には小川がありますが、土が溜まったり、
折れた木が水を堰き止めて草地に溢れていないかを
確認するために川沿いの草を刈払機で刈ました。
お昼に近づくと暑さも感じ、蚊にさされたこともあり、
次回からはしっかりと虫対策も必要だと感じました。
次回は7月6日(日)9:30集合になります


(記録、写真:太田)
参加者:6人
昨日は雨が降っていましたが今日は晴れ間が見える天気で一安心でした。
6月から開始が30分早い夏時間の集合となりました。
最初に管理地全体をみんなで歩いてまわり、緑地の状況を確認いたしました。
そして、今後の草刈り等管理の計画をみんなで考えました。
整備の中心は草刈りでした。ブタクサは根っこから丁寧に刈り取りました。
これにより、根から再び出てくることがないようになります。
刈り取った草は積み重ねておきました。
また刈払機を使い布田道から見える草地を重点的に刈ることにしました。
ここを歩く人が気持ちよく見えることを意図しています。
また奥には小川がありますが、土が溜まったり、
折れた木が水を堰き止めて草地に溢れていないかを
確認するために川沿いの草を刈払機で刈ました。
お昼に近づくと暑さも感じ、蚊にさされたこともあり、
次回からはしっかりと虫対策も必要だと感じました。
次回は7月6日(日)9:30集合になります


(記録、写真:太田)
農と緑の管理
2025.06.01
竹林と緑地の管理活動が生むもの
町田市には現在、約800か所の公園や緑地があり、四季折々の自然が私たちの暮らしを彩っています。これらの緑地が快適に保たれている背景には、市の管理とともに、私たちNPO法人「みどりのゆび」など市民の手による日々の活動があります。
私たちは、竹林や緑地の清掃・除草、また管理地周辺での枯れ木や倒木の情報提供などを通じて、自然環境の保全に取り組んでいます。こうした作業は一見地味に思えるかもしれませんが、地域の自然を守り、次世代へつなぐ大切な役割を果たしています。そして何より、仲間と共に緑の中で体を動かす時間は、心にも体にも心地よいものです。
今年は、楽しみにしていた春の「タケノコ祭り」が中止となりました。竹林管理の楽しみのひとつであるタケノコの収穫が不作だったためです。不作の理由には、昨夏の猛暑や少雨に加え、「裏年」と呼ばれる周期的な不作の年が重なったことが挙げられます。自然のリズムには逆らえませんが、だからこそ来年の豊作に期待しながら、日々の手入れを続けていきたいと思います。
また、樹木の管理においても課題がありました。昨年2月の大雪で倒れた竹林広場のシラカシに続き、今年は3月・5月・6月に、「関屋の切通し」周辺で倒木が発生し、道路の安全が脅かされる場面がありました。市の公園緑地課と道路課が連携して迅速に対応してくださいましたが、市民である私たちも、危険な木の兆候を見つけられるよう知識を身につけ、協力していくことが大切だと感じています。今後は、そうした知識を学べる機会づくりにも力を入れていきたいと考えています。
町田の自然は、多様な生き物が暮らし、植物が育ち、人々の心を癒してくれるかけがえのない財産です。この素晴らしさをより多くの方に知っていただきたく、今年11月16日(日)には緑地でのイベントを予定しています。日頃の活動を紹介しながら、自然の恵みを分かち合い、地域の皆さんとつながる機会になればと思っています。
皆さまのご参加を心よりお待ちしています.
一緒に町田の緑を守り、育てていきましょう。
(文:伊藤 右学)
竹林を快適空間に
裏作だからと諦めたタケノコは‥‥
3月23日(日)・4月13 日(日)
まずはびこっていた竹林広場の草を刈り、ここに念願の丸太の輪切りの椅子を設置しました。高さがちょうど良く座り心地抜群。下の段の竹林への階段造りにも着手しました。これもかねてからの念願のものです。
それと並行して、2月の雪の為に倒されて、処理しきれないでいたシラカシや竹もチェーンソーやノコギリで切り片付ける事が出来ました。
今まで少しづつ手をかけて見映えのいい竹林になって来ていたのに、倒木の光景はショックでした。でも木が倒れた分、竹林はもっと明るくなりました。
傍では、モミジイチゴの若い枝がスクスク伸びています。実のなる頃が楽しみです。
タケノコは4月13日の生育調査では5本しか採れなくて、裏作だから仕方ないと諦めていましたが、翌週には、なんと30本近くの収穫がありました。
この日、初めて参加の方にも喜んでもらえて嬉しかったです。これからの励みになります。
(文:鈴木 由美子)
タケノコ掘りに初参加
4月20日(土)
爽やかな春の陽気に恵まれ、新緑の竹林は清々しく、心身共に癒されました。
緑地管理にご尽力されている皆様方の企画実現の為の努力には、頭が下がる思いが致します。
4月20日の竹林には、タマノカンアオイ、アマドコロ、ニガイチゴ、カキドオシなどの野草、またサンショウの芽生えまで見られました。中でも、タマノカンアオイは絶滅危惧種だとか・・・・。

収穫したタケノコ(写真:伊藤)

タマノカンアオイ(写真:横山)
竹の根っこは、地下茎が横に広がり堅く、タケノコの周りの地面を掘る事は、私にはとても無理で急斜面を登るのがやっとの思いでした。
しかし、私と同年代の高齢者が、颯爽と斜面を登り降りする姿を拝見して、私も頑張らなくては、といった意欲が湧いてきました。
何事も経験だからトライしてみなさいとタケノコ掘りを指南してくださった方、また、斜面を登るのに棒を差し出して手助けをして下さった方など、心優しい方々に囲まれて、大変幸せな一日になりました。
(文:榎本 美智子)
凶作でタケノコ祭りは中止
来年の豊作を期待したい
4月27日(日)
3週連続のタケノコ掘りは、今回で事実上終わり。20本程度掘れたものの、全体に細く痩せており、シーズン末期の特徴を現しています。穂先刈りが出来るほど伸びていたのは、わずか2本だけでした。
タケノコは、年毎に概ね規則的な豊凶を繰り返しているようです。
今年は特に凶作であり、祭り行事も中止となりました。その分、来年は豊作が期待できると思います。
今日の天気は晴天で、午前中は気温も高くなく、極めて快適でした。木々の緑は日々濃くなりつつあり、里山の生命力をいただく思いがしました。
その後、有志7名はフットパスでも訪ねた鶴川香山園に移動。昨年12月開催した当会管理緑地と竹林を紹介したイベントの慰労会も兼ねて、「桜梅桃李」で和やかに昼食会を楽しみました。
(文:合田 英興)
夏に向かって大切な作業準備
5月11日(日)
5月にふさわしい青空の下、気持ちよく作業ができた。今回は緑地班と竹林班の二手に分かれて行なった。緑地班は布田道沿いの草を刈り、広い緑地の中に道を作るように刈払い機を使った。これで来月からの緑地管理がしやすくなる。
竹林班は穂先筍を切ったり密集している竹を間引いたりした。一段低い竹林への通路の端に穂先筍を見つけたが、こういう位置のものは通路の土を固めるためにも切らないほうが良いと教えてもらった。
通年募集中の 「みどりのボランティア」 に新しい会員の方が加わった。昨年12月の「里山再発見ツアー」に参加されたことがきっかけで、最近はフットパスにも参加されている。
(文:新納 清子)
今後の草刈りは、
暑さと虫対策が必須と実感
暑さと虫対策が必須と実感
6月1日(日)
昨日は雨が降っていましたが、今日は晴れ間が見える天気で一安心。最初に管理地全体をみんなで歩いて回り、緑地の状況を確認した後、今後の管理の計画を立てました。
今日の整備の中心は草刈りです。丈高くはびこったブタクサは、根っこから丁寧に刈り取りました。これにより、根元から再び出てくることがなくなります。刈り取った草は積み重ねておきました。
また刈払機を使い、布田道から見える草地を重点的に刈ることにしました。ここを歩く人が気持ちよく見えることを意図しています。
緑地の奥には小川があります。土が溜まったり、折れた木が水を堰き止めて草地に溢れていないかを確認するためにも、川沿いの草を刈払機で刈りました。
お昼に近づくと暑さが増し、蚊にさされたこともあって、次回からはしっかりと虫対策も必要だと感じました。

木陰から緑地をながめる

ニガイチゴも花をつけて(写真:横山)
(文と写真:太田 義博)

よく管理された竹林(写真:横山)
他のまちのフットパスをみてみよう 鷺宮フットパス阿佐ヶ谷から鷺宮へ
2025.05.23
[ 講師: みどりのゆび 浅黄 美彦 山本 愛子冨沢 みちこ ]
5月23日(金)天気:晴 参加者:17名
昨秋歩いた「阿佐ヶ谷~西永福町」の続編です。今回は阿佐ヶ谷駅から北へ、西武新宿線の鷺宮駅まで歩きました。新たな取り組みとして「中野たてもの応援団」で活動している鷺宮在住のお二人にサポートしていただきました。前回同様に古道、神社、川(暗渠)を辿りながら、古民家、戦前の郊外住宅地、公団住宅や鷺宮ゆかりの著名人の痕跡も訪ねてみました。
阿佐ヶ谷駅に集合、駅に近い「阿佐ヶ谷神明宮」で全体のコース説明を行い桃園川暗渠へ。暗渠とは、川や水路など水の流れに蓋をしたものです。その佇まい(景観)、うつろい(暗渠となった経過)、つながり(経路)を楽しむという「暗渠」の基礎知識を語りながら、迷路のような細道を北へ進むと「お伊勢の森児童公園」が見えてきます。

桃園川暗渠
お伊勢の森児童公園から杉森中学校にかけての一帯はかつて「お伊勢の森」と呼ばれ、阿佐ヶ谷神明宮の旧社地であった、かつての深い森のかすかな名残りの場所としてこの児童公園が整備されているようです。
「 鷺宮神明宮」、「相澤家の旧居」跡、旧道そして「桃園川暗渠」を歩くことで、市街化する前の近郊農村としての旧阿佐ヶ谷村の様子を想像してもらいました。

お伊勢の森児童公園
住宅地の細道を東に少し歩くと「A さんの庭」(旧近藤さんの家)、昭和初期に建てられた数軒の住宅が、生け垣をつらねて今も残る一角の中ほどに、庭木に埋もれるように、ひっそりとした佇まいを見せていたという。宮崎駿監督が、トトロが住みそうな面影の家々を訪ねた6軒のうちの一つです。
A さんの庭ができるまでもドラマのようで、不審火で焼けてしまった戦前の住宅はありません。しかし宮崎駿監督は、家の土台や井戸、庭などを残し、家を思い出させる赤瓦のトイレを盛り込んだ公園を提案し、これが承認されて2010年に「A さんの庭」と名付け開園したそうです。A さんとはここを訪れるすべての人のこと。みんなが自分の庭のようにここを大事にしてとの思いが込められている場所は心地よく、ここで昼食をいただきました。
 Aさんの庭
Aさんの庭
早稲田通りを横断して北へ少し歩くと、2軒目のトトロの住む家、中野区白鷺の「Tさんの家」跡があります。ケヤキ並木のある集落の道沿いにあったTさんの家も、残念ながら解体されてしまいましたが、2012年、この住宅のお別れの会に出席したという案内人のお二人のお話を聞きながら、その家の面影は感じることができました。
 ケヤキ並木にある白鷺のT さんの家跡
ケヤキ並木にある白鷺のT さんの家跡
次に訪ねた白鷺の茅葺屋根の旧家「細田家」は、幕末に移築された建物とのこと。その由来からこの建物の保存維持活動について、地元の山本さん、冨沢さんから解説をいただきました。広大な細田家の敷地の一部は、中杉通りの拡幅予定地だそうです。道路工事がなかなか進まず、時が止まったようなお屋敷となっていました。

細田家にて集合写真
細田家を後にして、日本住宅公団の実験的なテラスハウスで作家阿川弘之・佐和子一家も住んでいた「鷺宮住宅」、将棋の「内藤九段邸」、「坪井栄の自邸」跡、「遠藤新設計の住宅」など、地元民ならではの鷺宮の見所を案内していただきました。最後に美しくよく庭が管理された「福蔵院」を訪ね、ちょうどいらした、お二人の同級生でもある住職の奥様にお話を聞き、解散としました。

福蔵院にて
解散後に、地元の案内人のご配慮で、喫茶店「エルビエント」を貸し切っていただきましたので、美味しい珈琲をいただきながら歓談しました。
(文と写真:浅黄 美彦)

喫茶店エルビエントで
阿佐ヶ谷から早稲田通りを少し進むと、中野区と杉並区の境界にたどり着きます。その境界付近には、築 150 年とされる中野区最後の茅葺き民家が残っています。屋根にはトタンがかぶせられていますが、長年の重みにより傾きが進んでいる状況です。
この貴重な建物を守ろうと、「中野たてもの応援団」は毎月第 2 日曜日の午後に集まり、 約 20 名で広大な敷地(約 1000 坪)の清掃活動を続けています。また、伝統技法研究会という建築家の団体に依頼し、中野区文化財課が古い建物の悉皆調査を行いました。700 件以上の建物を調査し、記録を残したうえで報告書も作成しました。 その中には茅葺き民家や鷺ノ宮住宅も含まれていますが、残念ながら計画道路の建設 に伴い、鷺宮八幡神社社務所とともに取り壊される可能性が高い状況です。
私の祖父は三岸好太郎、祖母は三岸節子で、ともに画家です。祖父がデザインした三岸アトリエ(昭和 9 年築)も調査の対象となりました。祖父は「鷺ノ宮風景」という 題名の油彩画を残しています。"祖父の油彩画『鷺ノ宮風景』には、かつての妙正寺川 の穏やかな姿が描かれており、失われつつある景色がキャンバスの中で生き続けています。
(文:山本 愛子)
ご参考:「鷺ノ宮風景」三岸好太郎作
・下記に文化財遺産データーベース(文化遺産オンライン)
からご覧いただけます。
https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/233351
(みどりのゆび田邊博仁)
戦前からのよき街づくりの姿を体感
5月23日(金)天気:晴 参加者:17名
昨秋歩いた「阿佐ヶ谷~西永福町」の続編です。今回は阿佐ヶ谷駅から北へ、西武新宿線の鷺宮駅まで歩きました。新たな取り組みとして「中野たてもの応援団」で活動している鷺宮在住のお二人にサポートしていただきました。前回同様に古道、神社、川(暗渠)を辿りながら、古民家、戦前の郊外住宅地、公団住宅や鷺宮ゆかりの著名人の痕跡も訪ねてみました。
阿佐ヶ谷駅に集合、駅に近い「阿佐ヶ谷神明宮」で全体のコース説明を行い桃園川暗渠へ。暗渠とは、川や水路など水の流れに蓋をしたものです。その佇まい(景観)、うつろい(暗渠となった経過)、つながり(経路)を楽しむという「暗渠」の基礎知識を語りながら、迷路のような細道を北へ進むと「お伊勢の森児童公園」が見えてきます。

桃園川暗渠
お伊勢の森児童公園から杉森中学校にかけての一帯はかつて「お伊勢の森」と呼ばれ、阿佐ヶ谷神明宮の旧社地であった、かつての深い森のかすかな名残りの場所としてこの児童公園が整備されているようです。
「 鷺宮神明宮」、「相澤家の旧居」跡、旧道そして「桃園川暗渠」を歩くことで、市街化する前の近郊農村としての旧阿佐ヶ谷村の様子を想像してもらいました。

お伊勢の森児童公園
住宅地の細道を東に少し歩くと「A さんの庭」(旧近藤さんの家)、昭和初期に建てられた数軒の住宅が、生け垣をつらねて今も残る一角の中ほどに、庭木に埋もれるように、ひっそりとした佇まいを見せていたという。宮崎駿監督が、トトロが住みそうな面影の家々を訪ねた6軒のうちの一つです。
A さんの庭ができるまでもドラマのようで、不審火で焼けてしまった戦前の住宅はありません。しかし宮崎駿監督は、家の土台や井戸、庭などを残し、家を思い出させる赤瓦のトイレを盛り込んだ公園を提案し、これが承認されて2010年に「A さんの庭」と名付け開園したそうです。A さんとはここを訪れるすべての人のこと。みんなが自分の庭のようにここを大事にしてとの思いが込められている場所は心地よく、ここで昼食をいただきました。
 Aさんの庭
Aさんの庭早稲田通りを横断して北へ少し歩くと、2軒目のトトロの住む家、中野区白鷺の「Tさんの家」跡があります。ケヤキ並木のある集落の道沿いにあったTさんの家も、残念ながら解体されてしまいましたが、2012年、この住宅のお別れの会に出席したという案内人のお二人のお話を聞きながら、その家の面影は感じることができました。
 ケヤキ並木にある白鷺のT さんの家跡
ケヤキ並木にある白鷺のT さんの家跡次に訪ねた白鷺の茅葺屋根の旧家「細田家」は、幕末に移築された建物とのこと。その由来からこの建物の保存維持活動について、地元の山本さん、冨沢さんから解説をいただきました。広大な細田家の敷地の一部は、中杉通りの拡幅予定地だそうです。道路工事がなかなか進まず、時が止まったようなお屋敷となっていました。

細田家にて集合写真
細田家を後にして、日本住宅公団の実験的なテラスハウスで作家阿川弘之・佐和子一家も住んでいた「鷺宮住宅」、将棋の「内藤九段邸」、「坪井栄の自邸」跡、「遠藤新設計の住宅」など、地元民ならではの鷺宮の見所を案内していただきました。最後に美しくよく庭が管理された「福蔵院」を訪ね、ちょうどいらした、お二人の同級生でもある住職の奥様にお話を聞き、解散としました。

福蔵院にて
解散後に、地元の案内人のご配慮で、喫茶店「エルビエント」を貸し切っていただきましたので、美味しい珈琲をいただきながら歓談しました。
(文と写真:浅黄 美彦)

喫茶店エルビエントで
祖父・三岸好太郎の絵に今も生き続ける景色
阿佐ヶ谷から早稲田通りを少し進むと、中野区と杉並区の境界にたどり着きます。その境界付近には、築 150 年とされる中野区最後の茅葺き民家が残っています。屋根にはトタンがかぶせられていますが、長年の重みにより傾きが進んでいる状況です。
この貴重な建物を守ろうと、「中野たてもの応援団」は毎月第 2 日曜日の午後に集まり、 約 20 名で広大な敷地(約 1000 坪)の清掃活動を続けています。また、伝統技法研究会という建築家の団体に依頼し、中野区文化財課が古い建物の悉皆調査を行いました。700 件以上の建物を調査し、記録を残したうえで報告書も作成しました。 その中には茅葺き民家や鷺ノ宮住宅も含まれていますが、残念ながら計画道路の建設 に伴い、鷺宮八幡神社社務所とともに取り壊される可能性が高い状況です。
私の祖父は三岸好太郎、祖母は三岸節子で、ともに画家です。祖父がデザインした三岸アトリエ(昭和 9 年築)も調査の対象となりました。祖父は「鷺ノ宮風景」という 題名の油彩画を残しています。"祖父の油彩画『鷺ノ宮風景』には、かつての妙正寺川 の穏やかな姿が描かれており、失われつつある景色がキャンバスの中で生き続けています。
(文:山本 愛子)
ご参考:「鷺ノ宮風景」三岸好太郎作
・下記に文化財遺産データーベース(文化遺産オンライン)
からご覧いただけます。
https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/233351
(みどりのゆび田邊博仁)
【緑地管理報告 5/11(日)】
2025.05.12
5月11日(日)晴れ
10:00〜12:00
参加者 7名
5月に相応しい青空の下、気持ちよく作業が出来た。
緑地班と竹林班の二手に分かれて行なった。
緑地班は布田道沿いの草刈りや茂った草地の中に道を作るように刈払機で草を刈った。
広い緑地の中に道を作るようにしたのは来月からの緑地管理がしやすいためである。
竹林班は穂先筍を切ったり密集している所の間引きをした。
下の段に行く通路の端に穂先筍を見つけたが、こういう位置のものは通路の土を固める
ために切らない方がよいらしい。
嬉しい報告2件
①緑のボランティアに新しい会員の方が参加された。
昨年12月の里山再発見ツアーに参加されたことがきっかけで、この頃はフットパスにも参加されている。
②関屋の切通し近くの倒木は本日、少年野球チームの保護者さん達が大きなチェーンで丸太切りにして
みどりのゆびの竹林管理地側に片付けられた。
大事なお知らせ
6月から集合時間が夏時間に変わります。
6月1日(日)9:30集合
(記:新納)
10:00〜12:00
参加者 7名
5月に相応しい青空の下、気持ちよく作業が出来た。
緑地班と竹林班の二手に分かれて行なった。
緑地班は布田道沿いの草刈りや茂った草地の中に道を作るように刈払機で草を刈った。
広い緑地の中に道を作るようにしたのは来月からの緑地管理がしやすいためである。
竹林班は穂先筍を切ったり密集している所の間引きをした。
下の段に行く通路の端に穂先筍を見つけたが、こういう位置のものは通路の土を固める
ために切らない方がよいらしい。
嬉しい報告2件
①緑のボランティアに新しい会員の方が参加された。
昨年12月の里山再発見ツアーに参加されたことがきっかけで、この頃はフットパスにも参加されている。
②関屋の切通し近くの倒木は本日、少年野球チームの保護者さん達が大きなチェーンで丸太切りにして
みどりのゆびの竹林管理地側に片付けられた。
大事なお知らせ
6月から集合時間が夏時間に変わります。
6月1日(日)9:30集合
(記:新納)
他のまちのフットパスをみてみよう町田・野津田の里山にある「浮輪寮」と野津田公園フットパス
2025.05.10
[講師:みどりのゆび 田邊博仁]
5月10日(土) 天気:小雨・曇 参加者:17名
本日のFP(フットパス)の目玉は、「浮輪寮」です。
「野津田車庫」から、野津田の里山の小径を登ります。途中にある「浮輪寮」へのいくつかの案内板は手作りで、「ゆっくり~浮輪寮」と書かれ、浮輪寮のご主人の暖かい思いやりが伝わってきます。丘(104m)の上の「農村伝道神学校」に出て、そのキャンパスに入ると、大きなスズカケの巨木の右側に数寄屋造りの浮輪寮が見えてきました。

「ゆっくり~浮輪寮」の小径

浮輪寮と水鏡の池
「浮輪寮」の名は、1954(昭和31)年の青函連絡船洞爺丸事故で、日本人の若者に自分の救命胴衣を与えて亡くなった農村伝道神学校の創立者、カナダ人宣教師アルフレッドラッセル・ストーン牧師にちなんでいます。
今日は「浮輪寮」内で、建築家丸谷博男先生から、ビデオを使って、浮輪寮再生にまつわるお話を伺いました。素敵なトークとまさかのピアノ演奏にビックリ、そしてご自慢の体に優しい手作りの「ホワイトカレー」をいただきました。廊下越しに解放された窓からの庭、雨に濡れた森、水が張った池も素敵でした。

数寄屋造りの天井と廊下と外の緑

建築家丸谷博男氏
「浮輪寮」は2022年に再生され、里山の環境を学ぶ講座、古典落語、華道、茶道、上方舞、雅楽、音楽ライブ、朗読、ワークショップなど様々な目的に活用されています。
「浮輪寮」を後に、午後からは野津田の里山を歩きます。FPを始めた頃(約15年前)、このようなマップを作って楽しんで歩いていました。久しぶりに、作ってみました。

野津田の里山歩きフットパスマップ
このマップに従い、①野津田車庫から~③浮輪寮~⑤小野路一里塚~⑥野津田公園~⑨国内最大級12mの鎌倉古道発掘現場~⑩森のレストラン「俊宣茶房」をぐるり~と回るFPのご案内をしました。
野津田の里山の変遷(明治から昭和、平成、令和)を調べてみると、農村伝道神学校が野津田の広大な山林を購入後(1978(昭和33)年)から、各種施設ができています。
神学校の丘から歩き始めると、「都立町田の丘学園」、「都立野津田高校」と続き、さらに歩くと「きこえの学校ライシャワー学園」(「聾話学校」から2025/4 学校名変更)、「まちだ丘の上病院」(名誉院長が鎌田實氏。鎌田氏の「地域を支える医療」が病院の理念)と各種の施設・学校・病院が集まっています。

「ライシャワー学園」

「まちだ丘の上病院」
小野路へ向かう道を進むと、鎌倉時代からの古道が。江戸時代、家康の遺骨が久能山から日光東照宮に移された時(1617年)の御尊櫃御成道には、この時「小野路一里塚」が造られ、両脇にエノキの木が植えられました。その後、大山道として賑わいました。
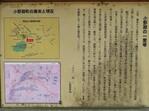
小野路一里塚の案内板
野津田公園に入ります。敷地面積は約121,000坪(東京ドームの約34.8個分相当)と広大な公園です。1990年に陸上競技場として開園。2020年には、町田GIONスタジアムが町田ゼルビアのホームグラウンドとして、2022年には、ばら園がここに移設されました。

野津田GIONスタジアム
「湿性植物園」へ入ります。公園調整池内に、1919年開園。現在はスケートパーク計画が進行中。
また、野球場の近くには「国内最大級12m幅の鎌倉古道」の発掘現場がありますが、発掘後の道路遺構は埋め戻され、公園の下に保存されています。
公園の続きの森に囲まれ閑静なレストラン「俊宣茶房」(しゅんせんさぼう)をご案内しました。農村伝道神学校の創始者であるストーン牧師の晩年の住居を改修したお店のようです。


閑静な森の中のレストラン「俊宣茶房」(2014,12)
森の中の小径を歩いて、野津田公園の「上の原ススキ草地」へ出ました。ここから、「華厳坂の鎌倉古道」を経て「野津田車庫」へ戻り、解散しました。
*下記のGoogleフォトのアルバムに全体の写真を掲載しています。下記のURLにてご覧いただけます。
【みどりのゆびFP「町田・野津田の里山にある「浮輪寮」と野津田公園フットパス(2025/5/10)】
https://photos.app.goo.gl/LNMqsJLUmhJkdSwq5
(文と写真:田邊 博仁)
◆丸谷先生のお話から二つ、感想。
①朽ち果てているとも見られる木造建築を、伝統技法も生かしながらここまで再生されたことに感銘を受けました。特に、自然から学んだ室内環境の創出は素晴らしい。浮輪寮は周辺の木々のたたずまい(雨模様が一段と美しく)ともあいまって、独特のちからを見る者に感じさせますね。
②浮輪寮や農村伝導神学校の歴史を伺うと、戦争が終わった後しばらくの時代の「熱」を思い出しました。ぼく自身の小学校(井の頭の明星学園)の時代です。子どもごころにも、自由・溌剌の時代でした。今思えば、民主主義への期待に溢れていた時代と言うのが可能かも。
そして今回のフットパスを企画された田邊さんの精力的で周到な準備作業には感謝あるのみ。ありがとうございました。たくさんの素晴らしい写真にもお礼。(高見澤邦郎)
◆NPOみどりのゆびのまち歩き『町田・野津田の里山にある「浮輪寮」と野津田公園フットパス』で、浮輪寮を訪ねました。
農村伝道神学校の学生寮として使われていた建物を、丸谷博男氏の改修設計により、見事に蘇った交流施設。丸谷さんから浮輪寮の謂れから出来上がるまでのお話を聞かせていただきました。本物のあるいは本気のエネルギーを費やして作られた建物の、凄みのようなものを感じました。
(浅黄 美彦)
◆昨日はありがとうございました。
雨が池に水紋となり数寄屋造りの建物の中ゆるりとした灯り、丸谷先生の講演とピアノ演奏、まるで異次元の世界でした。雨の中もなかなか良いですね。素晴らしい一日でした。(櫻田美知子)
数寄屋造りの古民家を再生した「浮輪寮」をバックに。ご自慢の手作りの「水鏡」に雨水がたまり、映し出される
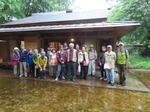
丸谷先生とみなさま
古民家を再生した浮輪寮を訪問野津田の里山を歩く
5月10日(土) 天気:小雨・曇 参加者:17名
本日のFP(フットパス)の目玉は、「浮輪寮」です。
「野津田車庫」から、野津田の里山の小径を登ります。途中にある「浮輪寮」へのいくつかの案内板は手作りで、「ゆっくり~浮輪寮」と書かれ、浮輪寮のご主人の暖かい思いやりが伝わってきます。丘(104m)の上の「農村伝道神学校」に出て、そのキャンパスに入ると、大きなスズカケの巨木の右側に数寄屋造りの浮輪寮が見えてきました。

「ゆっくり~浮輪寮」の小径

浮輪寮と水鏡の池
「浮輪寮」の名は、1954(昭和31)年の青函連絡船洞爺丸事故で、日本人の若者に自分の救命胴衣を与えて亡くなった農村伝道神学校の創立者、カナダ人宣教師アルフレッドラッセル・ストーン牧師にちなんでいます。
今日は「浮輪寮」内で、建築家丸谷博男先生から、ビデオを使って、浮輪寮再生にまつわるお話を伺いました。素敵なトークとまさかのピアノ演奏にビックリ、そしてご自慢の体に優しい手作りの「ホワイトカレー」をいただきました。廊下越しに解放された窓からの庭、雨に濡れた森、水が張った池も素敵でした。

数寄屋造りの天井と廊下と外の緑

建築家丸谷博男氏
「浮輪寮」は2022年に再生され、里山の環境を学ぶ講座、古典落語、華道、茶道、上方舞、雅楽、音楽ライブ、朗読、ワークショップなど様々な目的に活用されています。
「浮輪寮」を後に、午後からは野津田の里山を歩きます。FPを始めた頃(約15年前)、このようなマップを作って楽しんで歩いていました。久しぶりに、作ってみました。

野津田の里山歩きフットパスマップ
このマップに従い、①野津田車庫から~③浮輪寮~⑤小野路一里塚~⑥野津田公園~⑨国内最大級12mの鎌倉古道発掘現場~⑩森のレストラン「俊宣茶房」をぐるり~と回るFPのご案内をしました。
野津田の里山の変遷(明治から昭和、平成、令和)を調べてみると、農村伝道神学校が野津田の広大な山林を購入後(1978(昭和33)年)から、各種施設ができています。
神学校の丘から歩き始めると、「都立町田の丘学園」、「都立野津田高校」と続き、さらに歩くと「きこえの学校ライシャワー学園」(「聾話学校」から2025/4 学校名変更)、「まちだ丘の上病院」(名誉院長が鎌田實氏。鎌田氏の「地域を支える医療」が病院の理念)と各種の施設・学校・病院が集まっています。

「ライシャワー学園」

「まちだ丘の上病院」
小野路へ向かう道を進むと、鎌倉時代からの古道が。江戸時代、家康の遺骨が久能山から日光東照宮に移された時(1617年)の御尊櫃御成道には、この時「小野路一里塚」が造られ、両脇にエノキの木が植えられました。その後、大山道として賑わいました。
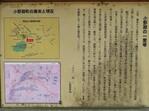
小野路一里塚の案内板
野津田公園に入ります。敷地面積は約121,000坪(東京ドームの約34.8個分相当)と広大な公園です。1990年に陸上競技場として開園。2020年には、町田GIONスタジアムが町田ゼルビアのホームグラウンドとして、2022年には、ばら園がここに移設されました。

野津田GIONスタジアム
「湿性植物園」へ入ります。公園調整池内に、1919年開園。現在はスケートパーク計画が進行中。
また、野球場の近くには「国内最大級12m幅の鎌倉古道」の発掘現場がありますが、発掘後の道路遺構は埋め戻され、公園の下に保存されています。
公園の続きの森に囲まれ閑静なレストラン「俊宣茶房」(しゅんせんさぼう)をご案内しました。農村伝道神学校の創始者であるストーン牧師の晩年の住居を改修したお店のようです。


閑静な森の中のレストラン「俊宣茶房」(2014,12)
森の中の小径を歩いて、野津田公園の「上の原ススキ草地」へ出ました。ここから、「華厳坂の鎌倉古道」を経て「野津田車庫」へ戻り、解散しました。
*下記のGoogleフォトのアルバムに全体の写真を掲載しています。下記のURLにてご覧いただけます。
【みどりのゆびFP「町田・野津田の里山にある「浮輪寮」と野津田公園フットパス(2025/5/10)】
https://photos.app.goo.gl/LNMqsJLUmhJkdSwq5
(文と写真:田邊 博仁)
浮輪寮を訪ねての感想
◆丸谷先生のお話から二つ、感想。
①朽ち果てているとも見られる木造建築を、伝統技法も生かしながらここまで再生されたことに感銘を受けました。特に、自然から学んだ室内環境の創出は素晴らしい。浮輪寮は周辺の木々のたたずまい(雨模様が一段と美しく)ともあいまって、独特のちからを見る者に感じさせますね。
②浮輪寮や農村伝導神学校の歴史を伺うと、戦争が終わった後しばらくの時代の「熱」を思い出しました。ぼく自身の小学校(井の頭の明星学園)の時代です。子どもごころにも、自由・溌剌の時代でした。今思えば、民主主義への期待に溢れていた時代と言うのが可能かも。
そして今回のフットパスを企画された田邊さんの精力的で周到な準備作業には感謝あるのみ。ありがとうございました。たくさんの素晴らしい写真にもお礼。(高見澤邦郎)
◆NPOみどりのゆびのまち歩き『町田・野津田の里山にある「浮輪寮」と野津田公園フットパス』で、浮輪寮を訪ねました。
農村伝道神学校の学生寮として使われていた建物を、丸谷博男氏の改修設計により、見事に蘇った交流施設。丸谷さんから浮輪寮の謂れから出来上がるまでのお話を聞かせていただきました。本物のあるいは本気のエネルギーを費やして作られた建物の、凄みのようなものを感じました。
(浅黄 美彦)
◆昨日はありがとうございました。
雨が池に水紋となり数寄屋造りの建物の中ゆるりとした灯り、丸谷先生の講演とピアノ演奏、まるで異次元の世界でした。雨の中もなかなか良いですね。素晴らしい一日でした。(櫻田美知子)
数寄屋造りの古民家を再生した「浮輪寮」をバックに。ご自慢の手作りの「水鏡」に雨水がたまり、映し出される
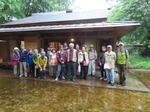
丸谷先生とみなさま
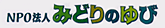
 2025.06.02 19:07
|
2025.06.02 19:07
| 


